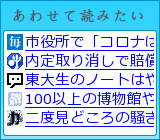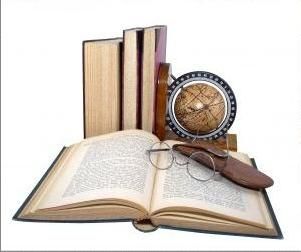記事検索
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ
2010年3月20日 11:00
診断基準からアスペルガー症候群が消える!?
アスペルガー症候群という名称を、最近はニュースなどでも時々耳にするようになったが、イギリスではとくに頻繁に取り上げられることが多くなっているようだ。アスペルガー症候群(アスペルガーしょうこうぐん、Asperger syndrome: AS)は、興味・関心やコミュニケーションについて特異であるものの、知的障害がみられない発達障害のことである。「知的障害がない自閉症」として扱われることも多いが、公的な文書においては、自閉症とは区分して取り扱われていることが多い。精神医学において頻用されるアメリカ精神医学会の診断基準 (DSM-IV-TR) ではアスペルガー障害と呼ぶ。・・・・・・
(Wikipedia「アスペルガー症候群」より引用)
(Wikipedia「アスペルガー症候群」より引用)
上記の説明にもあるとおり、自閉症にも共通する症状があることから、雇用に至るまでに立ちふさがる大きな壁があることに、社会的な関心が寄せられてきた。だが2013年出版予定であるDSMの第五版から、アスペルガー症候群の名称そのものがなくなることがわかった。
なぜ消えるのか
アスペルガー症候群の診断は一般的に、自閉症と比べてその重みが比較的軽いことが、診断名を削除するという決定につながったようだ。これに対し、アスペの患者の人格が否定されているという厳しい意見がある一方で、自閉症の一種として診断されるのだから、さまざまな支援を受ける上では何も変わっていないという意見もある。雇用面から見ると、そこに立ちふさがる壁は大きい。1944年にハンス・アスペルガー医師によって発見されたこの障害は、いわゆる「空気が読めない」というコミュニケーション上の弊害がある。就職に役立つスキルの習得に困難があったり、大学などで学ぶことに困難がある場合もある。社会的な成功に不可欠な、人脈という基礎を築くことが難しいのである。
これらの点から、アスペがある人の雇用は無理だ、と思われてきた。だが本当にそうなのだろうか。
「空気が読めない」彼らの適性とは
確かに、面接は相当厳しいものになる。コミュニケーション障害があると挨拶もぎこちなくなりがちだし、自分の言葉で話すことは難しいので、紙を読み上げるような応答になることもあるだろう。それだけで面接に落ちる要素としては充分だ。だがアスペがある人には、細かいことへのこだわり、特定分野への驚くほどの集中力、完璧に仕上がるまで何度も繰り返し行う忍耐力などがあるという見方もある。これらの素養は例えば、たった一つのバグのために延々と作業を繰り返さなければならないコンピュータ・プログラミングのような職業にはうってつけなのだ。順番などに固執するタイプの場合、万が一の間違いも許されないような仕事では、他の人が到底気付かないような小さな間違いに目ざとく気付くこともあるのである。
面接という壁をクリアしさえすれば、開ける道はたくさんある。確かに、同じスキルを持つ二人の求職者のうち一人がコミュニケーションに困難が見られれば、企業はほぼ間違いなくコミュニケーションに困難のない人を選ぶのが現実というものだ。だがそのような困難を身をもって知る人がその適性を見極められて採用されることで、採用側が次の応募者のコミュニケーション力不足を補うことも可能になるのである。
(編集部 小川優子)
Aspies are far from unemployable
-->
障がい者雇用 新着30件